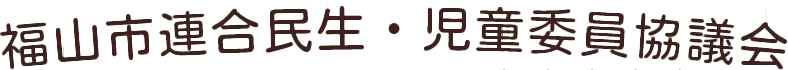よくある質問

【本分及び身分】(民生委員法第1条)
民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉の増進に努める方々です。
【任期・給与】(民生委員法第10条)
民生委員に給与は支給されません。任期は3年で、再任も可能です。ただし、任期途中で交代があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。3年に1度、一斉改選が行われ、最新の一斉改選は2022年(令和4年)12月1日に行われました。
【定数】(民生委員法第4条)
定数は、厚生労働大臣の定める基準に従って、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定めます。2022年(令和4年)12月1日現在の定数は、240,547人です。
【委嘱の仕組み】(民生委員法第5条)
都道府県知事は、市町村の民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通した者として推薦された者について、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。(児童福祉法第16条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。また、主任児童委員は、児童委員のうちから、厚生労働大臣が指名します。)2022年(令和4年)12月1日現在、225,356人の方が民生委員として委嘱され、活動しています。
【民生委員・児童委員の職務内容】
◆民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
- 1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
- 2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
- 4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
- 6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
◆児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
《児童委員》
- 1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
- 3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
- 5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
- 6.その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
《主任児童委員》
- 1.児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
- 2.区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
【職務遂行上の義務】(民生委員法第15条)
職務遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、平等な取扱いを行うという規定があります。
また、民生委員・児童委員は、民生委員法第14条において、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力することとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
民生委員・児童委員には、要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることが多いため、守秘義務が課せられています。
【地位を利用した政治活動の禁止】(民生委員法第16条)
職務上の地位を政治的に利用することは禁止されており、これに違反したものは解嘱されます。
【指揮監督権】(民生委員法第17条)
職務に関して、都道府県知事・指定都市長・中核市長の指揮監督を受けます。また、市町村長も、職務に関して指導を行うことができます。
【民生委員協議会】(民生委員法第20条、第24条)
民生委員は、区域ごとに民生委員協議会を組織することになっており、区域は、町村は一区域、市においては数区域に区分され、職務に関する連絡調整、必要な資料及び情報の収集など、職務を遂行するのに必要な事項を処理しています。